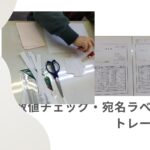大地震発生時の対処法と備蓄のポイント、障害者が被災した時はどうする?
災害はいつ、どこで起こるかわかりません。特に大きな地震が起きた時、その場にいる場所によって、取るべき行動は変わってきます。今回は、グループでディスカッション形式で話し合いました。
1. 大地震発生!その時どうする?シチュエーション別の対処法
電車内、エレベーター、そして屋外。これらの場所で大きな地震に遭遇したら、どう行動すべきか?参加者全員で意見を出し合い、具体的な対処法を話し合いました。
【電車に乗っている時】 走行中の電車内で大きな揺れを感じたら、まずは身の安全を確保することが最優先です。
- 座席に座っている場合: 座席の前にかがんで頭を守り、手すりや座席の脚をしっかり掴みます。
- 立っている場合: 周囲の手すりや吊り革をしっかりと握り、転倒しないように姿勢を低くします。
- 車掌さんの指示に従う: 揺れが収まった後も、むやみに窓から外へ出たり、勝手に非常扉を開けたりしないようにしましょう。車内アナウンスや車掌さんの指示に従って行動することが大切です。
【エレベーターに乗っている時】 エレベーターの中にいる時に揺れを感じたら、最も危険な状況の一つです。
- 全ての階のボタンを押す: 揺れを感じたら、全ての階のボタンを素早く押します。これは、エレベーターが最寄りの階で止まる可能性を高めるためです。
- 扉が開いたらすぐ脱出: 扉が開いたら、すぐにエレベーターから降り、非常階段を利用して避難します。
- 閉じ込められた場合: エレベーターが停止し、閉じ込められた場合は、非常用ボタンを押して外部と連絡を取ります。落ち着いて救助を待ちましょう。
【外を歩いている時】 屋外で地震に遭遇した場合、周囲の状況を冷静に判断し、安全な場所へ移動することが重要です。
- 建物や看板、電柱から離れる: 落下物や倒壊する危険があるため、建物や看板、自動販売機、電柱などから速やかに離れます。
- 頭を保護する: カバンや手で頭を守ります。周囲に身を隠せるもの(公園の広場など)があれば、そこに移動します。
- 落ち着いて行動する: 慌てて走り回ると、転倒して怪我をする恐れがあります。冷静に状況を判断し、落ち着いて行動しましょう。
2. 備蓄しておきたいものリストと「アルファ米」の備え
災害発生後、ライフライン(電気、ガス、水道)が復旧するまでには時間がかかります。一般的に、1週間から10日程度は自力で生活できる備えが必要と言われています。
【備蓄品の例】
- 飲料水: 1人1日3リットルを目安に7日分
- 食料: 缶詰、レトルト食品、カップ麺、栄養補助食品など
- 懐中電灯、携帯ラジオ、モバイルバッテリー
- 医薬品: 常備薬、絆創膏、消毒液など
- 衛生用品: 簡易トイレ、ウェットティッシュなど
災害時には、公衆電話やスマートフォンアプリなど、さまざまな情報収集手段があります。また、一部の自動販売機は、災害発生時に電力がなくても商品を取り出せる仕組み(災害対応ベンダー)になっている場合がありますが、自動的に無料になるわけではありません。無料提供されるかどうかは、設置者の判断によりますので注意が必要です。
そして、今回のディスカッションでも話題に上がったのが非常食**「アルファ米」**です。
アルファ米はなぜ必要? 一度炊いたご飯を乾燥させたもので、お湯や水を注ぐだけでご飯に戻る保存食です。軽くて持ち運びにも便利で、長期保存が可能です。「アルファ米は普段食べ慣れていないと、いざという時に食べるのに抵抗があるかもしれない」という話がセミナーでありました。非常時だからこそ、少しでも普段に近い食事ができることが心の安定につながります。一度試しに食べてみて、味や食感に慣れておくことをおすすめします。
障害をお持ちの方も、公的なサービスを待つだけでなく、日頃から自助(自分で備えること)と共助(地域で助け合うこと)の準備をしておくことが非常に重要です。
- 自助:
- 非常持ち出し袋の準備: 常用している薬や医療機器、携帯食、予備のバッテリーなど、個々の障害特性に合わせた備蓄品を用意しておきましょう。
- 避難訓練への参加: 地域で行われる避難訓練に積極的に参加し、避難経路や避難場所を確認しておきましょう。
- ヘルプカードの準備: 氏名や住所、連絡先、アレルギー、必要な支援内容などを記載したヘルプカードを常に携帯しましょう。
- 共助:
- 地域の交流: 近隣住民と日頃からコミュニケーションを取り、いざという時に助け合える関係を築いておくことが大切です。
- 支援者との情報共有: 普段から関わりのあるヘルパーやケアマネジャーなどと、災害時の連絡方法や避難計画について話し合っておきましょう。
日頃から「もしも」を想像しておくことで、いざという時に冷静に行動できます。今回ご紹介したポイントを参考に、ご自身やご家族に合った防災対策をぜひ見直してみてください。
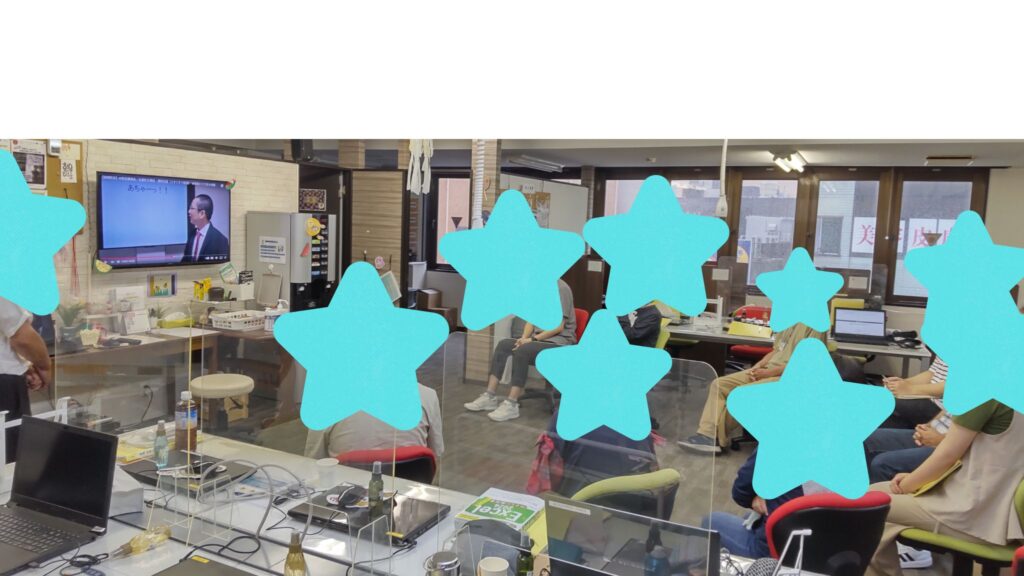




 Facebook
Facebook Twitter
Twitter instagram
instagram